谷地ひなまつり

河北町谷地の「ひなまつり」は、月遅れの4月上旬に北口通りを中心に行われ、「ひな市」が立ちます。
500年も前から谷地には毎月18もの市が立ち、大変な賑わいをみせていました。そのうち、谷地城主白鳥十郎長久公が開いた旧暦3月2日の市がちょうど雛の節句にあたるもので、いつしかそれが「節句市」、「おひな市」とよばれ、今日に至っています。市には雛人形・だるま・玩具などのほか、雛節句用の食品や一般日用品がならびます。まつりの主役は雛でありその昔、谷地が誇った紅花の取り引きで、京都などからの上方文化がこの地に導入され、雛もそのひとつでした。ここに伝わる数多くの享保雛や古今雛などは折紙つきの逸品で、美術書の巻頭を飾っています。そのほかにも、御所人形・竹田人形・からくり人形・鴻之巣人形・押絵雛などがあります。
雛への供えは、この地方独特のものとして、春告げ魚とよばれている鰊や田螺・野老・あさつき・慈姑・鶏卵・岩海苔の巻きずしなどがあります。しかも、これらを日々新しく供え替えする心のこまやかさもあります。
雛の飾りは一般に公開され、鑑賞に訪れた子どもたちには「ひなあられ」、「あま酒」などがふるまわれます。
雛の飾りは4月3日で終わりますが、それを延ばすと娘の婚期が遅れるとの言い伝えがあります。
谷地の「ひなまつり」が全国的に人の心をひくようになったのは、この小さな町に立派な雛が数多く残っていることと、その収集保存が全く庶民の手によって行われているからです。
代々、大切に引き継がれてきた絢爛たる「雛文化」を多くの方々に鑑賞していただき、より愛される「ひなまつり」にするようつとめています。
ひな供養の神事
雛の節句は、その昔から消厄除のこころをもりこんだまつりといわれ、今日でも地方によっては、日常生活での罪やけがれを素朴な紙びな(形代)に託し、川に流す風習などが残っています。谷地ひなまつりでは、秋葉神社境内の「ひな塚」の前で、古い雛や形代に雛料理を供え、私たちの健康と幸福を願う「ひな供養」の神事が行われます。

谷地ひなまつりフォトアルバム

ひな市

河北町紅花資料館の享保雛

ひな膳
この記事に関するお問い合わせ先
商工観光課 かほく発信・ブランド推進室 観光振興係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:331, 335
ファックス番号:0237-72-7333
お問い合わせフォーム
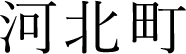






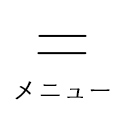

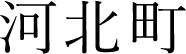



更新日:2025年01月29日