4.たばこ
進めよう受動喫煙の防止
行動指針
- 分煙された快適な生活環境を増やそう
- 未成年者の喫煙をなくそう
- 喫煙者は一度はたばこをやめてみよう
目標値
喫煙が及ぼす健康影響についての十分な知識を持っている人の割合の増加
中学生 52.7%から100%へ
乳幼児の保護者で毎日吸う人の割合の減少
21.3%から0%へ
公共施設の分煙、禁煙の推進
100%
町の実態
若い女性の喫煙率が高い
「分煙」そして「禁煙」の取り組みが全国的に進んでいますが、町内の喫煙の状況はどうでしょう。
アンケート結果から、町内の喫煙習慣者の割合は男性49.4%、女性11.9%で、女性の喫煙率は県平均(7.2%)より高く、とくに若い女性(20歳代39.7%)(乳幼児母親18.4%)に多くみられ健康被害が心配される結果となっています。
がん、低体重児などの影響
たばこを吸うと肺がんになる確率が高くなることは、よく知られています。しかし、たばこは肺がんだけでなく、多くのがん発症に大きくかかわっています。がんによる死亡率をたばこを吸わない人と比べた場合、食道がんは2.2倍、肺がん4.5倍、咽頭がんは32.5倍という結果がでています。
また妊婦がいる家庭での喫煙と、生まれてくる子供の体重との関係をみると、妊婦も夫も吸う場合は、2,500グラム以下の低体重児の赤ちゃんが生まれる割合が2.8倍に増えます。しかも夫だけが吸う場合だけでも1.7倍に増えます。
受動喫煙を防ごう!
健康増進法の施行
喫煙は本人だけの問題ではありません。たばこの有害物質は、たばこを吸う人が吸い込む煙(主流煙)よりたばこの先からでる煙(副流煙)のほうが何倍も多く含まれています。
たばこを吸う人のそばにいて副流煙を吸い込むことを受動喫煙といいます。受動喫煙を防ぐためには、人前でたばこを吸わないこと(分煙)が必要です。
また、5月からは健康増進法が施行され、「不特定多数の人々が利用する施設等の管理者は受動喫煙の防止に努めなければならない」と定められました。このことを受け、県内でも学校敷地内や、公共施設などを完全禁煙にするところが増えてきています。
町での禁煙教室
「やめたいけれど、やめられない」というのがたばこの怖さです。そんな人のために、町では平成13年度から「禁煙教室」を開催しています。一人ではくじけそうだけれど、一緒に励ましあう仲間がいれば成功する確率も高くなります。
みなさん、ぜひ思いきってたばこをやめてみませんか。
町の禁煙教室プログラム
- 医師講演
- マイクロスモーカーライザー測定(たばこに含まれる有害成分・一酸化炭素濃度の測定)
- ニコチンガム・ニコチンパッチの正しい使い方
- たばことアルコールの関係
- 体重が増えないための生活管理
- グループワーク(仲間同士の励まし合い、過去経験者の成功談・失敗談)
- 個別相談
この記事に関するお問い合わせ先
健康福祉課 健康づくり係
電話番号:0237-73-2111(代表) 内線:127~129
ファックス番号:0237-72-7333
お問い合わせフォーム
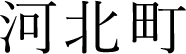






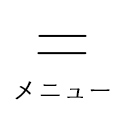

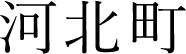



更新日:2023年03月31日